価格を最適化し、「ダイナミックプライシング」でOTA販売で単価と稼働アップ収益を最大化(レベニューマネジメント)
目次:
OTAでの販売、マーケティングに関わっている方は、最近、レベニューマネージメント とダイナミックプライシングという用語を 耳にするのではないでしょうか。この2つの用語は混同されがちで、これらの違いを把握している方は意外と少ないと思います。また、宿泊施設のレベニューマネジメント(もしくはダイナミックプライシング)でも都市型ホテルと旅館などのリゾート型では分析や運用がかなり違うことは知られていません。このページでは、基本から概要を説明していきます。
レベニューマネジメントについてはページ後半で後述します。
レベニューマネジメントとダイナミックプライシングは混同されやすいのですが、ごくごくシンプルに言うと以下の通りです。
レベニューマネジメント 収益を最大化するための総合的な販売戦略
ダイナミックプライシング 動的な価格のコントロール
ダイナミックプライシングは、レベニューマネジメントの一要素です。ただし、多くの場合で、レベニューマネジメントとほぼ同じ意味で利用されています。それはなぜかというと「価格調整」こそがレベニューマネジメントの中核であり、基盤だからです。
この2つの用語は、価格戦略の要素です。前述したようにレベニューマネジメントはダイナミックプライシングを内包しており、同じ意味で使っても問題はありません。
レベニューマネジメント(収益の改善)は、OTAや直販での販売の際に、最適な価格を適用することがメインと考えられます。この主たる取り組みが「ダイナミックプライシング」です。具体的には価格と稼働(販売数)を最適な状態に持っていくことと考えればいいでしょう。(実際に、ほぼ全てのケースで適切にダイナミックプライシングを行えば、単価と稼働は確実にアップします。)
働き方や休暇の取り方が多様化し、平日のニーズも以前より高まりつつあります。夏休みに集中したニーズも、少子高齢化、地球温暖化もあってイベントなども秋にずれ込んできています。
その流れの中で、宿泊業や観光業も平日や閑散期の旅行の需要を掘り起こすことが盛んになってきました。この需要を掘り起こすための動機づけの一つが平日や閑散期の「価格による施策」であるわけです。
旅館やホテルなど一般的に宿泊業は「状況によってニーズが変わる」という性質を持ちます。「ダイナミックプライシング」とは「状況によって価格が変えること」です。つまり宿泊業にダイナミックプライシングを組み合わせて価格を最適化することで収益を改善していくことが「レベニューマネジメント」と言えるでしょう。また、余談ですがカテゴリー的には価格戦略の要素の一つです。
ダイナミックプライシングは、価格戦略の重要な要素です。マーケティングとは「宿の魅力を高め売りやすくすること」ですが、それに対してダイナミック・プライシングの役割は「その魅力を効率的に価格に変換して収益を最大化」ということになります。
価格決定とは、商品の価値を「価格」に変換するための準備と言えます。(収益を改善するための)適切な価格は商品の価値、需要により変動します。その価格が適切かどうかの判断は、多くの場合、利益を確保しながらよく売れることです。逆に言えば、この価格設定を間違えれば、いくら価値があっても「売れるものも売れない」という事態に陥ります。
いくら高単価でも販売が少なければ意味がありません。よく売れても利益率が低ければ問題です。このように「値付け」というのは難しいわけで、 ダイナミックプライシングを運用するには「値付け」について仕組みを理解して合理的に行うノウハウが必要です。
つまり、ダイナミックプライシングというのは、うまく販売するために価格面で最適解を出し、利益を出す手法と言えます。
誤解されている方が多いのですが、ダイナミックプライシングとは「安売りして稼働を上げる」という意味ではありません。目的は収益の改善です。 実際のダイナミックプライシングは売上や単価や稼働を睨みつつ、収益の改善のためにコントロールしていきます。そして単価を上げることもダイナミック・プライシングの目的の一つです。
おそらく誤解の大元は、都市型のホテル(ビジネスやシティホテル)では極端に価格を調整してるためだと思われます。
メモ:都市型とリゾート型のダイナミックプライシングやOTA販売戦略の違いをvol.2で取り上げる
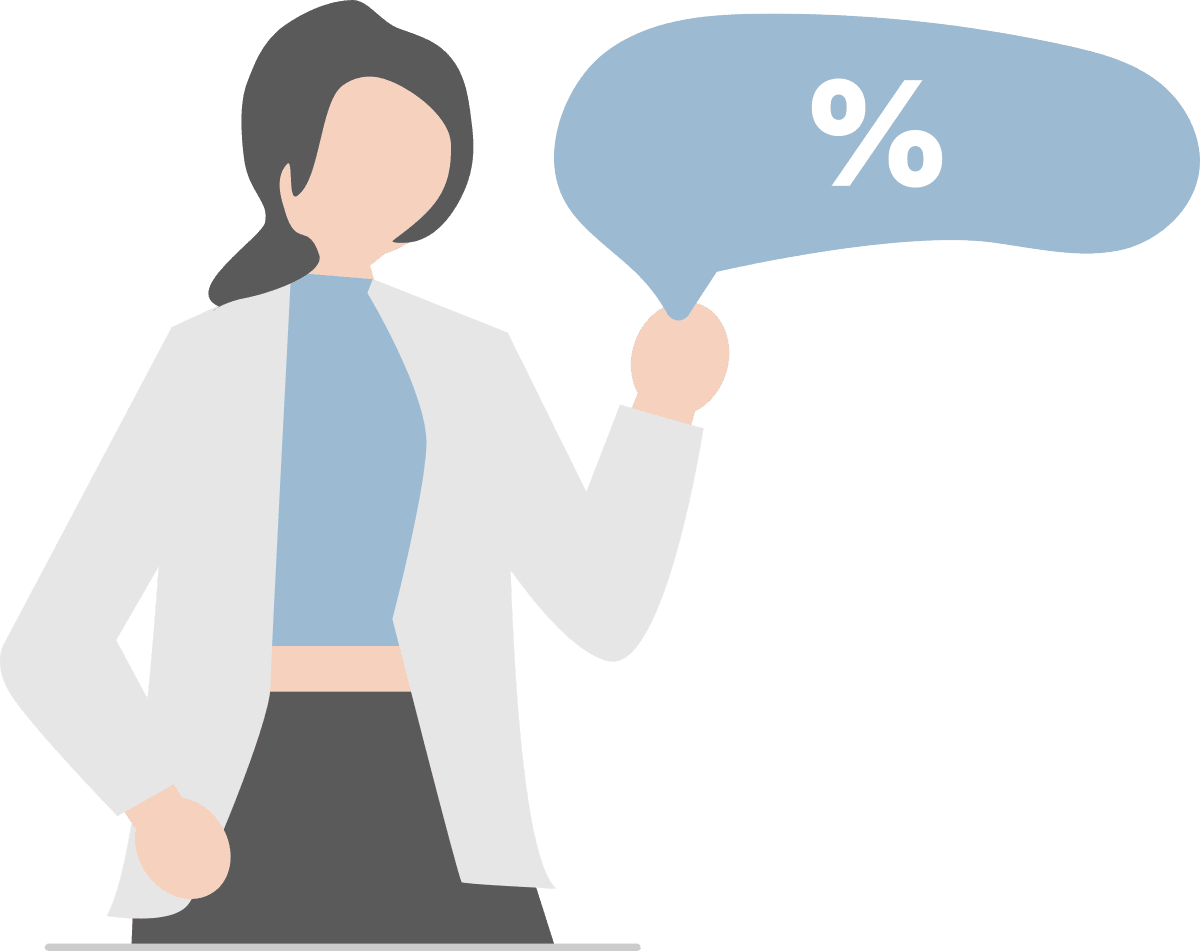
条件を満たした施設は、適切にダイナミックプライシングを行うと自然に「収益が改善」していきます。そのしくみをシンプルに言えば単価と稼働の掛け算を最適化することと言えばいいでしょうか。
経済学の基本中の基本とも言えますが、一般的に商品の価格が上がれば販売数は下がり、価格を下げれば販売数は増えていきます。さらに売上は価格と販売数の掛け算です。 つまりダイナミックプライシングはこれらの仕組みも利用していきます。
コストと需要が釣り合わず売れない場合、製造者や販売者は価格を下げる努力をします。そのために有効なのがたくさん販売して利益を上げる方法です。しかし宿泊業は客室は1日いくつまでと限界があるので、その限界の中で収益を改善しなければなりません。
当然ですが宿泊業は今日の在庫は持ち越せません。倉庫に在庫を積み上げることはできませんので、ダイナミックプライシングで価格が変動することを社会が許容してると言えます。つまりこの条件をうまく使いこなすことが旅館やホテルなど宿泊ビジネスの収益を改善するのです。
ダイナミックプライシングは、席に数に限りがあるが、日によって商品のニーズが変化するビジネス(航空業界やプロスポーツのチケット販売)で活用されつつあります。宿泊業界も類似したビジネスであり、「在庫に限りがあって、その価値は、その日のうちに消えてしまう」ビジネスです。
また「固定費が大きい業種」でもあるため、機会損失が収益に与える影響はとても大きくなります。つまり売り逃しこそ致命的になるということです。しかし一方で変動費比率が比較的小さいので、損益分岐点を超えてしまえば急激に利益を上げることができる性質も持っています。(これを営業レバレッジという)。つまりこれらの性質や条件がレベニューマネジメント、ダイナミックプライシングという手法が発達させた理由です。
需要が高ければ、単価を上げることで、客または室あたりの利益率はアップします。しかし人気の日に高い価格設定をするということは、昔から日本の宿泊業界で行われてきたことですので目新しくありません。しかしダイナミックプライシングは別モノとされています。旧来の手法と何が違うのでしょうか。
旧来の手法でも繁忙の度合いによって高価格に設定してきましたが、その値幅(価格のレンジ)は限りがありましたし、またニーズの変化に応じて効率的に動かすことは限定的でした。しかし適切に価格変動(ダイナミックプライシング)を行うことで、この効果を高めることができます。
ダイナミックプライシングを運用していない旅館やホテル(特にリゾート型)が陥りがちなのは、繁忙期や繁忙日は満室、その逆に、平日は稼働率が低くなり機会損失(つまり売れない状態)が起こる状態です。この状態を宿泊業界は甘んじて受け入れてきたところがあるのですが、この「空いている状態」をできるだけ減らすために、価格を下げる調整して需要を掘りおこしていきます。
価格を下げれば販売数が増えるといっても、価格を下げすぎたら収益はそれほど改善しません。なので、この単価と販売数を最適化するために様々な分析や判断のノウハウが必要です。これが案外落とし穴になっていて、仕組みもわからないまま価格調整しても結果がでないということにつながるわけです。
ダイナミックプライシングを運用していくと「稼働の平準化」という効果も見えてきます。説明が長くなりそうなので、詳細は控えますが、ここらへんを含めて価格戦略について、何かコンテンツを追加しようと思います。
ダイナミックプライシングで収益を改善すると言っても、仕組みを説明している方は少なく、多くのコンサルも理解してなかったりしてるんじゃないかと感じています。これらの仕組みを理解しないとダイナミックプライシングの運用は難しいとは思いますので、「ダイナミックプライシングやります」というセールストークにしかなってないのではないかと考えています。
リゾート系宿泊施設(旅館、リゾートホテル、グランピング、ゲストハウス、民泊など)では、都市型宿泊施設とは違ったダイナミックプライシングの運用が必要です。
リゾート型の宿泊施設(旅館など)と都市型(シティホテル・ビジネスホテル)では、もはや別のビジネスと言えるほどの違いがあります。価格決定モデルも異なります。その理由は、予約までの期間(リードタイム)が異なること、そして都市型が機能面で比較されやすいのに対し、リゾート型は「ここに泊まりたい」という動機が強く、代替性が低い点にあります。
リゾート型(旅館など)を利用目的は「非日常の体験」であり、大切な人と過ごす特別な時間を過ごすことです。そのため、口コミやその宿の魅力やコンセプトに対してユーザーは鋭敏な感覚を持っています。それに対して都市型(シティホテル・ビジネスホテル)の宿泊施設は、機能性を評価の中心として、リゾート型に比べれば「吟味して選ぶ」という傾向が低いといえます。これはユーザーにとっての適正価格が定量的に算出できず、感情や印象に左右されると考えています。
(特にリゾートの場合)質や口コミが十分に高い状態であれば、ダイナミックプライシングで単価は自然と上がっていきます。もし十分な質、魅力や口コミがなければ効果は限定的となります。
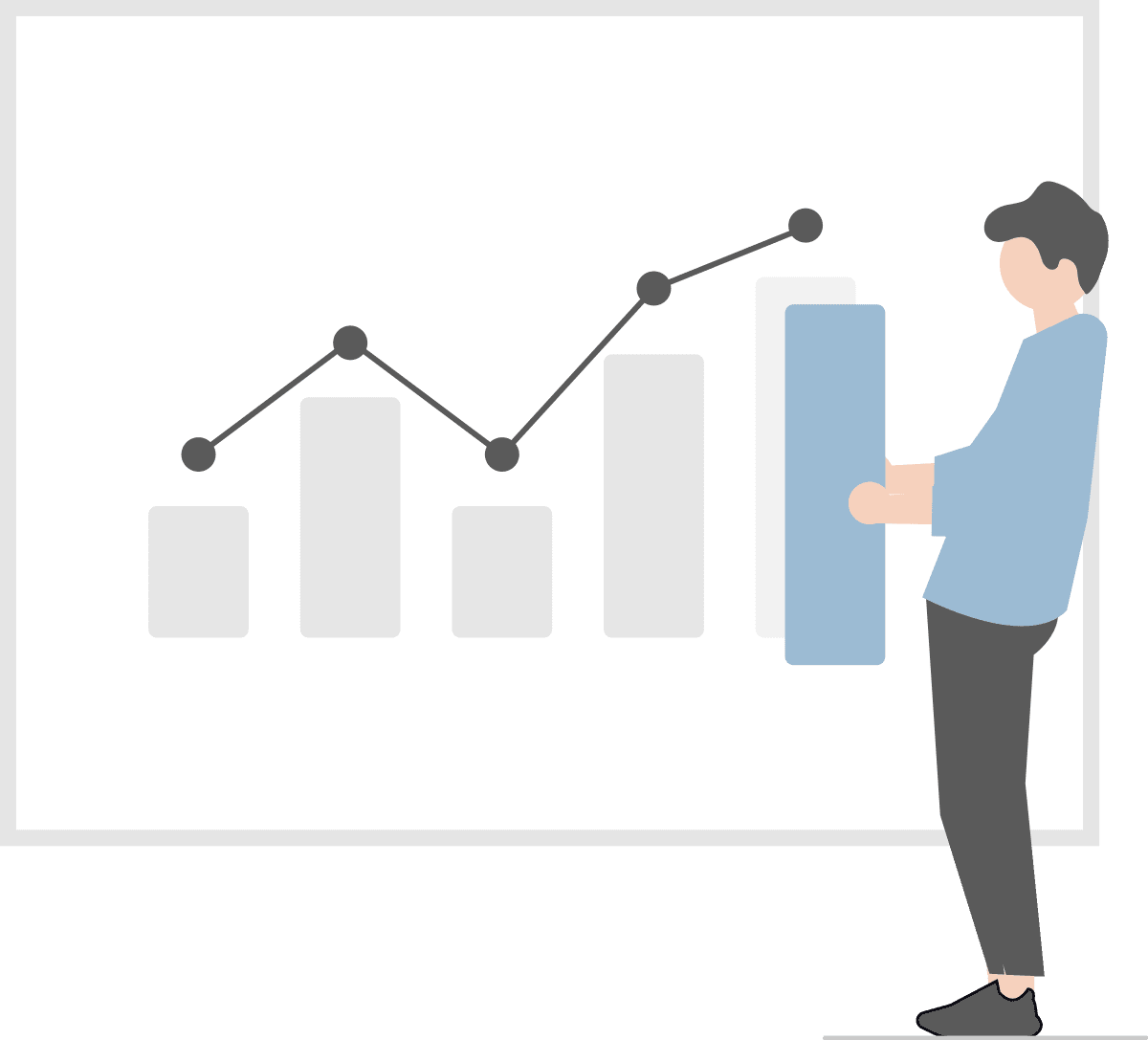
近年の宿泊施設のマーケティングでは、レベニューマネジメントという用語を耳にするようになりました。しかしこのレベニューマネジメントを日本語にすると「資産管理」という意味になり、意味を知ると宿泊施設の予約販売とのつながりがピンとこないのではないでしょうか。

マーケティングや販売戦略での用語としては 「在庫に限りがあり、需要が時間によって変動するビジネス(航空業界、宿泊業界など)で収益を最大化させる戦略」としています。
つまり、収益の最大化の手段として「価格や販売チャンネルなどを総合的に考えて販売すること」であり、その中に先述の「ダイナミックプライシング」が存在します。
目的:収益の最大化
手段:販売戦略、施策
もし価格を変動させるという意味に絞るならば「ダイナミックプライシング」を使うことをおすすめします。逆にダイナミックプライシングを含む「収益最大化のための総合的な販売戦略」という意味なら「レベニューマネジメント」を使うと明確になると思います。

人材不足「OTA販売担当者がいない」ノウハウ不足「OTAで売れない」
売上が低迷「売上が落ちた」
コンサルに不満「仕事が遅い」「提案がない」
公式サイト「売れる公式サイトに変えたい」
Web更新業者「作業が遅い」
OTA販売を改善したい方、気軽にお問い合わせください。 OTAを担当するスタッフに相談できます。