価格を最適化し、「ダイナミックプライシング」でOTA販売で単価と稼働アップ収益を最大化(レベニューマネジメント)
目次:

レベニューマネジメント(Revenue Management)とは、需要予測に基づき、価格などを最適化することで、限られた供給から最大の収益を得る管理手法です。ここでは主に旅館やホテル、グランピングなどの宿泊施設を対象にレベニューマネジメントを説明していきます。価格変動つまりダイナミック・プライシングについては、別のページで説明しています。合わせてチェックしてみてください。
ダイナミック・プライシングはレベニューマネジメント密接な関係があります。しばしば同義に扱われますが、厳密にはRMの中核を成す要素です
シンプル言えば、需要予測などマーケティングをしながらダイナミック・プライシング(価格調整)で収益改善する取り組みと定義していいと思います。
レベニューマネジメントというのは、価格調整(ダイナミックプライシング)こそが中核となっていますが、OTA上での価格調整・露出最適化・レビュー管理などを統合した運用全体を指すといえます
MTXでは、レベニューマネジメントを 「マーケティングを行いつつ、ダイナミック・プライシング(価格調整)によって旅館やホテルの価値を価格に変換し、収益を改善すること」と考えています。
ホテルや旅館は、一定期間の客室という“時間付きの空間”を販売しているため、その期間を過ぎれば価値が失われます。そのため、その日までに売り切らなければ「機会損失」となります。しかしレベニューマネジメントを適切に運用すれば、この「機会損失=売り逃し」を抑制することができます。
宿泊料金は、ニーズによって変動することがユーザーが許容しています。なので価格を変動させても一般的に受容されます。ですので、ニーズが低ければ稼働を上げるために安くしたり、ニーズが高ければ単価(利益率)を高くすることが可能です。ただし、その旅館やホテルのブランディングの面で制約はかかることもあります。
レベニューマネジメントは元々航空業界で収益改善の手法として生まれましたが、昨今では航空業界だけでなくスポーツ観戦やイベントなどのチケットにレベニューマネジメント(ダイナミック・プライシング)が取り入れられています。もちろん旅館、ホテル、グランピングなど宿泊業全般に実施されています。
どのようなビジネスで効果があるのかを紐解きます。
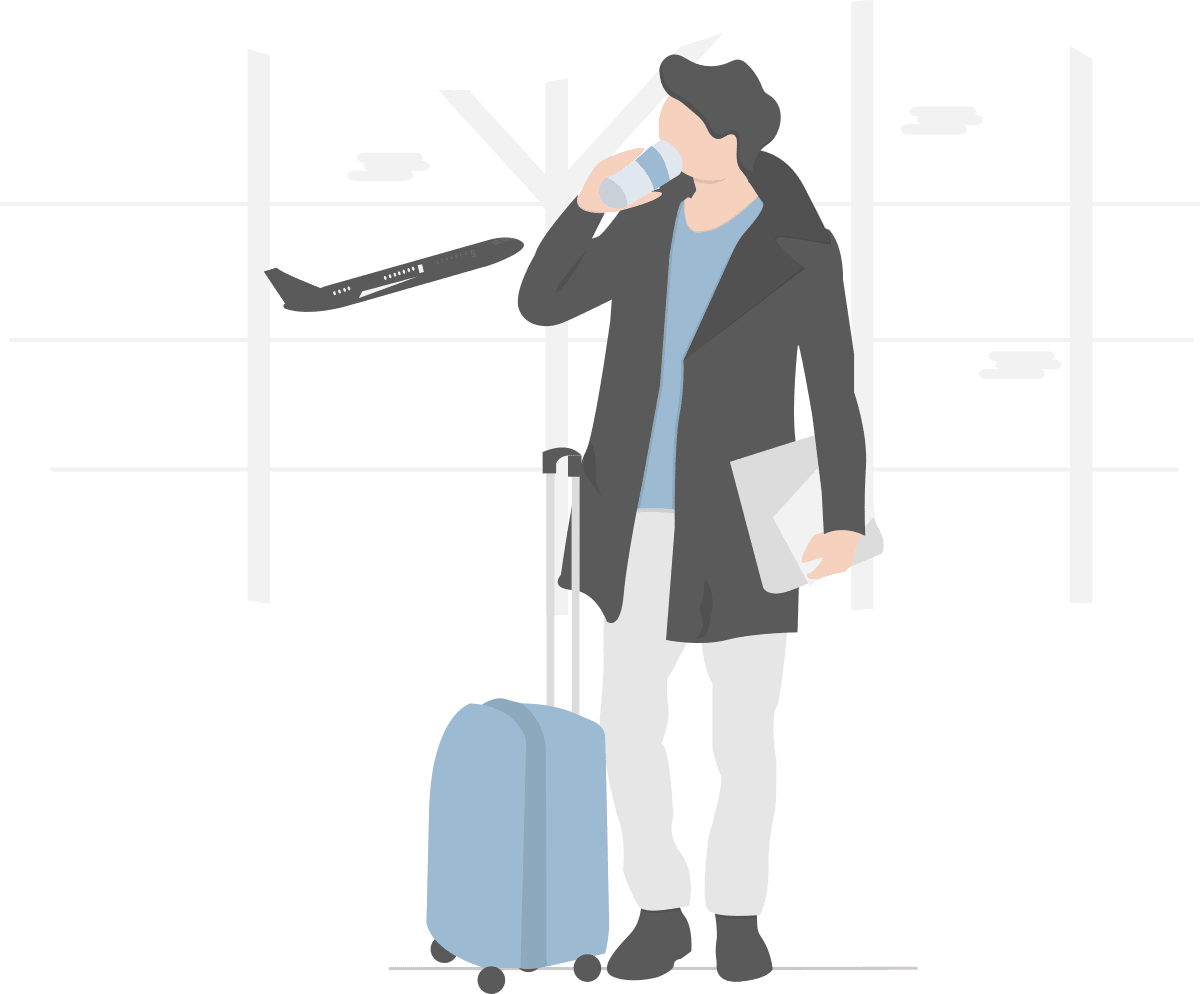
提供時間や期日が過ぎると、商品価値が完全に消滅してしまうビジネスに効果があります。例えば期限の過ぎた、映画のチケットなどは全く価値がなくなりますよね。旅館やホテルも同様に消滅する前に売らなければ収益はゼロになります。そこで、価格を柔軟に変えてでも完売を目指すことでレベニューマネジメント(ダイナミック・プライシング)は効果が大きいのです。
提供能力(キャパシティ)を増やせないビジネスで効果を発揮します。(例: ホテルの客室数、飛行機の座席数は変更できない)つまり、需要に応じて供給を増やせないので限られた供給量の中で価格と販売数を最適化する必要があります。
曜日、時間帯、季節などによって需要が大きく変動するビジネスで効果を発揮します。スポーツ、イベント、旅館やホテルも該当します。このようなビジネスでは予測する需要の精度を高め、レベニューマネジメント、ダイナミックプライシングで収益が改善します。
同じ商品やサービスであっても、ニーズなどによって価格変動がユーザーに受け入れられているビジネスで効果を発揮します。旅館やホテルなどでは従来から繁忙日(お盆や正月)に特別料金が設定されたり、閑散期には低料金が設定されていることにユーザーは慣れていますので戦略的に価格を変動させることが可能です。
旅館・ホテルなどの宿泊業はハイリスク・ハイリターン型のビジネスです。すなわち「好調時には大きく利益を上げ、低迷時には損失が拡大しやすい」構造を持ちます。その要因の一つが営業レバレッジです。
営業レバレッジが高いとは、固定費が大きく、変動費率(変動費/売上高)が低い状態を指します。売上が増えても変動費があまり増えないため、固定費を超えた売上分がそのまま利益に反映されやすくなります。これが「売上の変化に対して利益が大きく動く=レバレッジが効く」状態です。
固定費が大きく変動費率が低いビジネスでは、一定の売上を確保しなければ固定費が経営を圧迫します。これは大きな初期投資を要する宿泊業に典型的です。需要が低い時期でも稼働を維持し、売上を確保することが重要です。
一方で、変動費(直接原価率)の割合が低いため、粗利が大きくなります。損益分岐点を超えた売上は、そのまま利益に直結しやすく、価格をわずかに上げるだけでも収益改善につながる特徴があります。
旅館、ホテル、グランピングなどの宿泊業は、この2つの条件を満たす典型的な業種であり、レベニューマネジメントを適切に導入することで経営改善が期待できます。
レベニューマネジメントについて前提となる知識や経緯をまとめました。
1978年、アメリカで航空業界の規制緩和(航空自由化)が実施され、多くの航空会社が自由に価格設定を行えるようになって生まれました。
飛行機の座席(搭乗券)は、その搭乗日までに売れなければ売上がゼロという性質があります。(他の製品や商品は在庫としてその日以外にも売ることができる)。そのような航空業界の事情や条件の中で、航空会社がどのように販売すれば収益を最大化できるかという視点で生み出された考え方、戦略です。
もともと航空会社はリース会社から航空機を購入またはリースして、必要な人材を雇用し、どれだけの利益を回収できるか。という視点でモノを考えています。
海外のホテルの場合、所有者が建物を運営会社にリースする。そして運営会社はその運営によって利益を上げるという形が主流です。つまり、ホテル経営も航空業界に類似するビジネスモデルです。
2つの業界のいう「収益性」は、座席や客室という資産から、どれだけ有効に販売するかに掛かっています。このような事情から「レベニューマネジメント=価格を変動させて収益」という意味として使われるようになったと考えています。
日本の旅館などでは伝統的に、その所有者自体が経営(運営)を行っていることが主流です。しかし、海外では建物の所有者と、経営や運営が分かれていることが多いという歴史的背景の違いがあります。
| 役割 | 主な内容 | 代表例 |
|---|---|---|
| 所有者(オーナー) | 不動産を保有・投資 | 不動産投資ファンド、個人投資家、企業など |
| 運営会社(オペレーター) | ホテルの実務運営 | マリオット、ヒルトン、アコー、ハイアットなど |
| ブランド(フランチャイザー) | ブランド名と運営ノウハウ提供 | 上記運営会社がブランドも提供するケースが多い |
最近、プリンスホテルが、自社所有の資産を投資ファンドに売却して、運営に特化していくという記事を読みました。つまり海外の経営スタイルに合わせたということになります。
海外では、所有者と運営会社は分かれている事が多く、施設の所有者は経営または運営会社などにリースして「家賃」で収益を上げます。そして経営または運営会社は、その建物(施設)を運営して宿泊客に「短期に又貸し(宿泊)」するような形で利益を上げます。ちなみにこの配分の基準となるのが「GOP」と呼ばれるものです。

人材不足「OTA販売担当者がいない」ノウハウ不足「OTAで売れない」
売上が低迷「売上が落ちた」
コンサルに不満「仕事が遅い」「提案がない」
公式サイト「売れる公式サイトに変えたい」
Web更新業者「作業が遅い」
OTA販売を改善したい方、気軽にお問い合わせください。 OTAを担当するスタッフに相談できます。